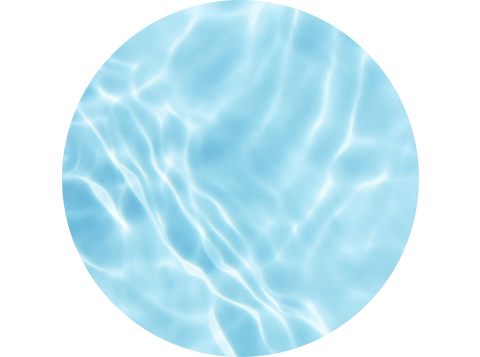「こどもの睡眠時間が短いかもしれない」
「こどもが睡眠不足になるとどんなリスクがあるの?」
とお悩みの方はいらっしゃいますか?
寝つきや寝起きが悪かったり、
短い時間しか寝なくて日中に眠たくなっていたり、
こどもの睡眠不足にはさまざまな問題がありますよね。
そこで、こちらの記事では年齢別のこどもの適切な睡眠時間を紹介し、
睡眠不足になった場合のリスクや睡眠の質を高めるコツ、
水分補給の重要性についてを詳しく紹介します。
こどもの睡眠について悩んでいる人は、
ぜひ最後までチェックしてみてください。
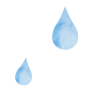
( 1 of 4 )
年齢別の適切なこどもの睡眠時間をチェック
まず、年齢別の適切な睡眠時間について、表にまとめました。
| 年齢 | 推奨睡眠時間 |
| 0〜3ヶ月 | 14〜17時間 |
| 4〜11ヶ月 | 12〜15時間 |
| 1〜2歳 | 11〜14時間 |
| 3〜5歳 | 10〜13時間 |
| 6〜13歳 | 9〜11時間 |
| 14〜17歳 | 8〜10時間 |
上記の内容を踏まえて、さらに詳しく解説していきますね。
年齢が上がるにつれ、睡眠時間は短くなる
表からもわかるとおり、生まれたばかりの赤ちゃんが最もたくさんの睡眠時間を必要としていて、年齢が上がるごとに推奨睡眠時間は短くなります。
また、生まれたての赤ちゃんは、1日の中で寝たり起きたりを繰り返しますが、だんだんと生活リズムができ、まとめて寝られるようにもなります。
生活リズムは自然についていく一方で、さまざまな原因から睡眠不足になってしまうことも多いです。
日本のこどもは睡眠不足の傾向が高い
日本のこどもたちは学業や習い事などで多忙な日々を送るため、睡眠不足になることが多い傾向があります。
先ほど紹介した年齢別の適切な睡眠時間に足りていないケースが多いので、我が子はどの程度睡眠をとっているかぜひ計算してみてください。
( 2 of 4 )
こどもの睡眠不足によるリスクは?
こどもが睡眠不足になると、どのような問題があるのでしょうか?
「少しぐらい睡眠不足でも大丈夫」と油断せず、起こりうるリスクを把握しておくようにしましょう。
記憶力や集中力を低下させる
十分な睡眠を取れていないと、こどもの記憶力や集中力が低下する可能性があります。
これにより、勉強の成果が出なかったりさまざまな活動に影響を及ぼすこともあるかもしれません。
しっかりと睡眠をとることで脳が活発に働くため、勉強や運動、日々のさまざまな活動もスムーズに行うことができるでしょう。
身体の発達に影響することも
睡眠はこどもの身体の発達に重要な役割を果たします。
生活リズムが整っていると、睡眠中に成長ホルモンが分泌され、骨や筋肉を成長させたり新陳代謝が活発になります。
睡眠不足になったり生活リズムが乱れたりすると、しっかりとホルモンが分泌されなくなり、身体の発達に悪影響があるかもしれません。
肥満のリスクが高まる
睡眠不足は食欲を増加させるホルモンの分泌を促すため、肥満のリスクを高めることがあります。
グレリンというホルモンが増えることで食欲が増加してしまうため、お菓子などを暴食してしまうリスクが高まります。
適切な睡眠を確保すればホルモン分泌が正常に戻るので、体重管理につながるでしょう。
免疫が下がり病気にかかりやすくなる
十分な睡眠を取らないと免疫機能が低下し、こどもが感染症にかかりやすくなる可能性があります。
こどもが幼稚園や学校に通っていると、感染症をもらいやすくなりますが、睡眠不足の状態だとよりうつりやすくなる可能性があるので注意が必要です。
質の高い睡眠は、免疫力を高めてくれます。
イライラしたり怒りっぽくなったりする
睡眠不足はこどもの行動にも影響を及ぼすことがあり、イライラや怒りっぽさなどの問題行動が起こりやすくなることもあります。
こどもが感情をコントロールできていないと感じる人は、睡眠がしっかりとれているか振り返ってみましょう。
適切な睡眠をとることで、穏やかに過ごす時間が増えると考えられます。
こどもとはいえ必要な睡眠時間には個人差があるため、必ずしも上記の体調不良などの原因が睡眠不足かどうかはわかりませんが、1つの目安にしてみてくださいね。
( 3 of 4 )
こどもの睡眠の質を高める具体的なコツ
こどもの睡眠の大切さがわかったところで、こどもの睡眠の質を高めるコツを具体的に紹介します。
良くない環境になっていたり、下記のような行動をしていると気づいた人は、良い習慣を作れるようにできることからはじめてみましょう。
室温を適温に保ち、快適な寝具を用意する
こどもの寝る環境は、快適であることが大切です。
夏は冷房を25〜27℃程度に、冬は暖房を20〜 23℃程度に設定しましょう。
また、季節に合わせた寝具を選んで、暑すぎず寒すぎない環境を整えてみてください。清潔で気持ちよく寝られる寝具を使うのも睡眠環境を整えるには大切なことです。
早起きに意識を向け、生活習慣を整える
朝早く起きる習慣を育てることで、体内時計が整い、夜の睡眠もスムーズになることがあります。
規則正しい生活リズムを確立するために、毎日同じ時間に起きる習慣を作ることをおすすめします。
夜早く寝てくれないと悩んでいるなら、遅寝になった場合でもひとまず朝早く起こす習慣を作るのが重要です。
起きてくれない場合はカーテンを開けて、日の光を取り入れたり、朝ごはんを食べさせて活動させたりしてみましょう。
寝る前にスマホやゲームを見ない
スクリーンからの青い光はメラトニンの分泌を妨げる可能性があるため、寝る1時間前からはスマホやゲームを避けましょう。
代わりに、リラックスできる行動をするのが睡眠の質を向上するのに役立ちます。
絵本を読む、軽いストレッチをする、静かな音楽を聴くなどスクリーンを使わないリラックス方法を試してみましょう。
寝る1時間前ぐらいに入浴する
お風呂は、寝る1時間前を目安に入るのが、睡眠の質を高めるのに効果的です。
なぜなら温かいお風呂に入ることでリラックスし、さらに温まった身体が徐々に冷めることで眠りに入りやすくなるからです。
お風呂後はゆっくりとくつろぎ、リラックスした状態でベッドに入ることで、ぐっすりと深い眠りにつくことができるでしょう。
( 4 of 4 )
こどもの睡眠中はたくさん汗をかく!
睡眠中は、体温を調節するために汗をかくものです。大人よりも体温が高いこどもは、より多くの汗をかくこともあります。
そのため、脱水予防のためにしっかりと水分補給をするのが大切です。水分補給のタイミングや習慣を身につけるためのポイントを紹介します。
睡眠中の脱水予防に寝る前に水を飲む
こどもが寝る前にコップ1杯の水を飲むことで、夜間の脱水を防ぐことができます。
小さなお子さんはたくさん水を飲むとおねしょが気になるので、無理のない範囲で補給するようにしましょう。
朝起きてからもしっかりと水分補給をする
朝起きたら、睡眠中に失われた水分を補給することを忘れずに行うのが大切です。
朝食の前にコップ1杯程度の水を飲むことで、身体に水を行き渡らせましょう。
ウォーターサーバーで摂取の習慣をつける
水分補給の習慣がないという方は、ウォーターサーバーを家に置くことでこどもが手軽に水分を摂る習慣を身につけることができます。
清潔な水が常に利用でき、手軽に飲める環境を整えることで、こどもの健康をサポートしていきましょう。
(summary)
こどもの睡眠の質を高めましょう

こちらの記事では、こどもの適切な睡眠時間や睡眠不足のリスク、良質な睡眠への促し方などを詳しく解説しました。
こどもの健康や成長のために、しっかりとした睡眠時間を確保することや睡眠の質を高めることを意識していきましょう。
夜寝られず朝起きられなくて悩んでいるお子さんは、まず少し無理をして早起きすることで、徐々にリズムが整っていきます。
日中元気に活動できるように、早寝早起きや水分補給の習慣を身につけてみてくださいね。