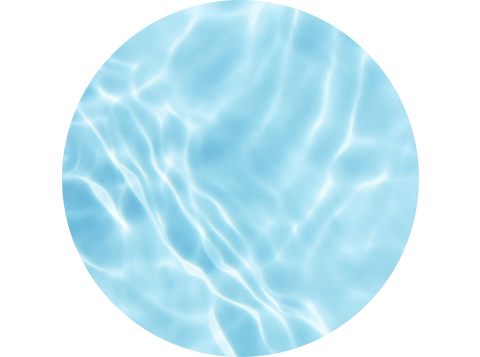暑い季節はたくさん汗をかきますが、汗かきの人は「なんでこんなに汗をかくの?」「汗かきをどうにかしたい」と悩みますよね。
この記事では、汗をかく理由と汗をかきすぎる要因を解説しています。
あわせて汗かきを予防する方法も紹介していますので、汗かきで悩まれている人はぜひ参考にしてくださいね。
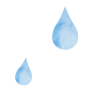
( 1 of 7 )
汗をかく理由
汗は暑い季節やスポーツをしているとき、お風呂に入っているときなど、さまざまなシーンでかきます。
汗には体温を一定に保つ役割があり、気温が高いときや体内の代謝が上がったときに、体温を下げるために汗をかくのです。
かいた汗が蒸発するときにエネルギーが必要となり、そのエネルギーが気化熱として体の表面の熱を奪うため、体温が下がります。
( 2 of 7 )
汗がベタベタしてニオイがするのはなぜ?
汗かきに悩んでいる人は、汗のベタベタ感とニオイにも悩まされていないでしょうか。
汗がベタベタする理由は、汗腺のろ過機能が衰えているからです。
汗は血液の成分がもとになってろ過され、汗腺というところから出てきます。
この汗腺のろ過機能が正常に働いていると、サラサラした水っぽい汗をかきます。
しかし汗をかく習慣がないと汗腺のろ過機能が衰えてしまい、ベタベタした汗となるのです。
ベタベタした汗はミネラルが多く含まれており、このミネラルが皮膚の常在菌と結合することで嫌なニオイのする汗になります。
ニオイの無いサラサラした汗にするには、日頃から汗をかく習慣づくりをし、汗腺のろ過機能を使うことが大切です。
( 3 of 7 )
汗をかきすぎるのは多汗症かも
汗は体温を一定に保つために必要なことですが、汗をかきすぎるのは多汗症かもしれません。
多汗症とは気温が高くなくスポーツをしたわけでもないのに、さまざまな要因によって日常生活に影響を及ぼすほどの汗をかくことです。
多汗症は全身に汗をかく全身性多汗症と、手のひらや足の裏、脇や顔など部分的に汗をかく局所性多汗症の2つに分けられます。
次の項目では、全身性多汗性と局所性多汗症の要因をそれぞれ紹介します。
( 4 of 7 )
全身性多汗症の要因
全身性多汗症の主な要因は以下があります。
更年期障害
更年期障害による汗は、特に閉経後の女性に起こりやすいです。
女性ホルモンであるエストロゲンは汗を抑える役割がありますが、閉経後はエストロゲンの分泌量が減ることにより、急激に汗をかくケースがあります。
また更年期障害によるのぼせやほてり、カーっと熱くなる症状をホットフラッシュといいます。
冷え性
冷え性の人は血のめぐりが悪いことから体が冷えやすく、加えて夏は冷たいものを飲んだり食べたりするので内臓が冷えて水分をため込みやすくなります。
本来、汗は体温調節のためにかきますが、冷え性の場合はため込んだ余分な水分を外に出すためにたくさん汗をかくのです。
暑い季節は水分補給を頻回にしますので、特に水の温度に注意が必要です。
ウォーターサーバーがあれば冷水、常温水、温水を使い分けることができるため、水分補給にぴったりですよ。
病気
内分泌や代謝系の病気であるバセドウ病や糖尿病、神経の病気であるパーキンソン病も汗をかきすぎる要因のひとつです。
その他にも汗をかく要因となる病気がありますので、汗のかきすぎが気になる人は病院への受診をおすすめします。
薬の副作用
薬の中には汗をかく副作用がある薬があります。
薬を内服中で汗をかきすぎる人は、かかりつけ医に相談してみましょう。
( 5 of 7 )
局所性多汗症の要因
局所性多汗症の主な要因は以下があります。
精神的な緊張
精神的な緊張による汗は、人前に出たときにドキドキしたり、ストレスがかかったりしたときにかくものです。
手のひらや足の裏、ワキに汗をかくことが多く、緊張したときに一気に汗が出る特徴があります。
辛いものを食べたとき
辛いものを食べたとき、香辛料の刺激によって額や鼻に汗をかくのも局所性多汗症の要因です。
辛いものを食べ終わり少し経つと、すみやかに汗が引くのが特徴です。
病気(原発性局所多汗症)
局所的多汗症の中でも明らかな要因がないものは、原発性局所多汗症という病気であることがあります。
原発性局所多汗症は最初に症状が起こる年齢が25歳以下と若いことが多く、左右非対称に汗をかくことや睡眠中は汗がとまることが特徴です。
( 6 of 7 )
汗のかきすぎとニオイは予防できる
汗のかきすぎとニオイは、以下の方法で予防ができます。
ただし、病気による汗のかきすぎは専門の医師による診断と治療が必要ですので、気になる人は病院への受診をおすすめします。
適度な運動をする
適度な運動をすることで、汗をろ過する汗腺の機能が改善し、適切な量のサラサラの汗をかけるようなります。
急激に汗をかく運動では、汗腺のろ過機能がしっかり働かないので、ゆっくり汗をかける有酸素運動をしましょう。
エアコンの温度設定を調節する
エアコンの温度設定が低めに調節されていると、汗腺が上手く働かず機能が衰えてしまいます。
夏の室温は28℃がちょうど良いとされており、エアコンを低い温度に設定している人は調節しましょう。
エアコンの温度を22℃から28℃に変更する場合、温度差が6℃と大きく、急に変更すると体に負担がかかるかもしれません。
日数をかけて徐々に設定温度を変更し、体を慣らしていきましょう。
食生活を見直す
肉や魚に含まれる動物性タンパク質や、チーズや牛乳などの動物性脂肪、ニンニクは汗のニオイの要因となります。
しかしタンパク質や脂肪は栄養素として必要ですので、食べ過ぎないことや野菜も取り入れた食事をすることが大切です。
また動物性タンパク質の量を減らして植物性タンパク質を取り入れても良いでしょう。
大豆には植物性タンパク質が多く含まれています。
また大豆の成分であるイソフラボンは女性ホルモンに似ているため、更年期障害による発汗を抑える効果が期待できます。
生活習慣を見直す
喫煙やアルコールの習慣も、汗のかきすぎやニオイの要因です。
タバコに含まれるニコチンは汗腺を刺激する作用があるため、必要以上に汗をかくことがあります。
またアルコールにより体温があがると汗をかき、アルコールが体内で分解されると汗や皮膚から刺激の強いニオイが発せられます。
喫煙とアルコールの量を控えるだけでも、汗やニオイの軽減が期待できるでしょう。
ストレスをため込まない
汗のかきすぎの要因のひとつに精神的な緊張があり、ストレスをため込まないことで汗のかきすぎを予防できます。
ストレスを解消するには、お風呂に入ってリラックスできる時間をつくることや、夜眠る時間を確保して休息することも大切です。
また自分の好きなことをする時間をつくっても良いでしょう。
( 7 of 7 )
体を温める
体の冷えは汗をかきすぎる要因となるため、体を温めることで予防ができます。
特に夏はエアコンの効いた部屋で過ごすことが多く、冷えを感じやすいです。
エアコンの温度設定を調節し、体を冷やしすぎないようにしましょう。
職場で温度設定の調節が難しい場合は、上着やひざ掛けを活用し、冷えないように工夫しましょう。
またお風呂にゆっくり浸かることでも体を温められます。
高い湯温だと汗が一気に出るため汗腺がしっかりろ過できず、全身湯船につかると汗が蒸発しないため、37℃~38℃くらいの半身浴がおすすめです。
(summary)
気持ちの良い汗をかこう

汗は体温を調節する役割があり、特に暑い季節は体温が上がりやすいため汗をかきやすいです。
汗をかいた分、水分補給を忘れずしましょう。
またウォーターサーバーでの水分補給は、ミネラルを取り除いたRO水でなく、ミネラルも含んだ天然水のウォーターサーバーがおすすめです。
そして汗は体温調節だけでなく、さまざま要因によって汗をかくこともあります。
汗のかきすぎやベタベタした汗は、運動や生活の習慣、環境の調整によってサラサラした適度な汗にすることが期待できます。
ただし病気による汗のかきすぎは専門の医療機関での治療が必要ですので、汗のかきすぎに悩んでいる人や、汗のかきすぎが改善しない人は受診しましょう。