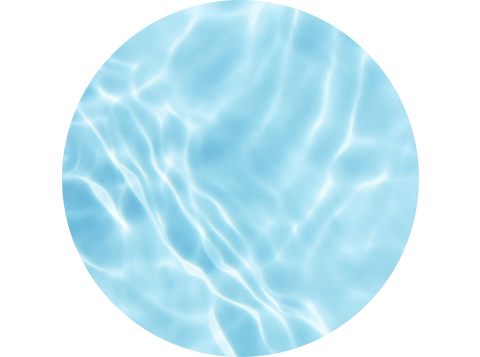さまざまな食べ物をおいしくいただくために重要な「味覚」。
私たちは食べ物を口に入れ、舌にのせることで甘味や酸味、苦味などさまざまな味を感じることができますよね。
この味覚は、こどものころの食経験の中で育まれると言われています。
そこで今回は、さまざまな食材をおいしく食べられる味覚を身に付けるため、こどもの味覚の発達の流れや味覚を育てるコツを詳しく紹介していきます。
こどもの味覚を豊かで繊細に育てたいと考えている親御さんは、ぜひ最後まで確認してみてください。
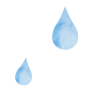
( 1 of 3 )
こどもの味覚の発達の特徴
こどもの味覚を育てるためには、まず味覚の特徴を知っておく必要があります。
食材の味わいの種類やこどもの好きな味わいについて、詳しく確認しておきましょう。
基本の味わいは5つある
こどもの味覚の発達には、まず味わいの基本である「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「旨味」を知る必要があります。
食材の味には上記の5つがあり、それぞれに役割があるので以下の表をご覧ください。
| 甘味 | エネルギー源である糖の存在を伝える役割 |
| 塩味 | ミネラルの存在を伝える役割 |
| 旨味 | たんぱく質の存在を伝える役割 |
| 苦味 | 毒があるかもしれないことを伝える役割 |
| 酸味 | 腐敗した状況を伝える役割 |
大人が好む食べ物の味わいには「辛味」があるものもありますが、こちらは刺激による痛みや温覚であることから、味わいには分類されません。
上記の中で、特に甘味が好きなこどもが多いものですが、これにはきちんと理由があります。
こどもが甘味が好きなのは本能
こどもが甘味を好むのは、生まれつきの本能的なものです。
それは、甘味が生きていく上に必要なエネルギーの存在を示してくれる味わいだからだと考えられています。
また、同じように旨味や塩味も人が生きるのに必要な味わいなので、こどもだけでなく大人も含めた人に好まれる味わいだと言えます。
そのため、生まれたての赤ちゃんが生きていくために飲む母乳は、本能的に好む甘味が強い味となっていて旨味や塩味も感じられるものとなっているのです。
苦味や酸味は経験の中で好むようになる
本能的に好む味わいに対して、苦味や酸味はこどもには好まれない傾向があります。
これらは、その2つの味わいが「毒」や「腐敗」のシグナルだからです。
しかし、成長とともにさまざまな食べ物に触れていく中で、苦味や酸味をおいしく感じるようになっていきます。
はじめは苦手でも、少しずつ取り入れていくことで好みの味になっていくこともあるので、さまざまな味わいや食材を経験させてあげることが大切です。
( 2 of 3 )
こどもの味覚の発達の流れ
それでは、こどもの味覚はどのような時期にどのような形で発達していくものなのかを確認していきましょう。
こどもが初めて食べ物を口にする離乳食初期のころからの成長を、詳しくお伝えしていきます。
生後5ヶ月を目安に離乳食を開始し、食べ物の味を知る
こどもの味覚の発達は、離乳食の開始がはじまりです。
生後5ヶ月を目安に離乳食をスタートし、最初はお米のおかゆや野菜や果物のペーストを食べさせます。
離乳食の時期にさまざまな食材の味を経験することで、先ほど紹介した基本的な5つの味わいに触れることができます。
初めての食べ物を口にしたときの興味津々な表情は、味覚の成長を実感できるものとなりますね。
味覚の発達は3〜4歳ごろがピーク
3〜4歳ごろには、味覚の発達がピークに達します。味を感じる舌の器官を「味蕾(みらい)」といいますが、味蕾は生まれたてのころが1番数が多く加齢と共に減少します。
こどもの方が大人よりも味蕾が多いため、より敏感にさまざまな味を感じられるのです。
そして3〜4歳のこどもたちは徐々に甘味や塩味、酸味、苦味、旨味を識別し、違いを感じるようになります。
この時期にバラエティ豊かな食材を食べさせ、新しい味わいに触れる機会を与えることで、味覚の感度が高まっていくことでしょう。
10歳ごろまでの食経験が味覚の基礎に
大人になってからの味覚や味わいの好みは、10歳ごろまでの食経験が影響を与えるといわれています。
10歳までにさまざまな食材を食べる経験を積むことで、好き嫌いが少なく、幅広い味わいを楽しむことができる基盤が築かれるということです。
親御さんのサポートによって多彩な食材を楽しむ経験が、こどもの味覚の発達を促す重要な要素となることを知っておいてくださいね。
( 3 of 3 )
こどもの味覚を豊かに育むコツ
さて、では実際にこどもの味覚を豊かに育てていくためのコツやポイントを確認していきましょう。
楽しくさまざまな食材の味に触れる機会を増やすことが、こどもの味覚を育むコツだといえます。順番にチェックしてみてください。
よく噛んで食べるように促す
味を感じる味蕾は舌だけでなく上顎やのどなど幅広い場所にあるため、口をもぐもぐと動かしてよく噛むことで、さらに味を感じられるようになります。
また、食材をよく噛んでいるうちに「はじめは甘味を感じたけれどだんだん旨味が出てきた」というような味わいの変化を感じることもできるでしょう。
しっかりと噛んで食べることで、すぐに飲み込んでしまうときとは違う味覚の経験を積ませることができますよ。
料理の味付けは薄味に
こどもに食べさせる料理の味付けは、控えめな薄味を心がけましょう。
濃い味付けに慣れてしまうと、こどもの味覚を鈍くしてしまうことがあります。
素材の持つ風味や味わいを大切にし、こどもたちが本来の味を楽しむ機会を作りましょう。
食べにくくない調理法を心がける
こどもにとって食べにくい形や食材は、味覚を楽しむ障害になります。
たとえば、筋の多い噛み切れないお肉や繊維質の野菜は、もし味が好きだと思ってもこどもにとって食べにくさが勝ってしまうかもしれません。
調理法を工夫して食べやすい形状にしたり、やわらかく噛み切りやすくしたりすることで、こどもたちに食事は楽しいものだと伝えることもできますよ。
ジュースではなくお茶や水を中心に
こどもの味覚を育てる上で、飲み物も大切なポイントです。
ジュースよりもお茶や水を中心に摂るよう心がけましょう。
ジュースの味わいは甘味が中心なのでこどもが依存しやすく、水分補給をジュースばかりに頼ると肥満や虫歯になるなど悪影響が多いです。
一方、お茶や水はシンプルな味わい味覚形成の邪魔をせず、健康的な飲み物としてこどもたちの成長をサポートします。
おいしい水をきちんと飲む習慣を身に付けるなら、ウォーターサーバーを生活に取り入れるのもおすすめです。
こどものジュース依存については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
(summary)
こどもの味覚を豊かに育んで

こちらの記事では、こどもの味覚を育てるために知っておきたい基本的な情報を紹介し、味覚の発達の流れや味覚を豊かに育てるコツを紹介しました。
こどものうちにさまざまな味わいを経験することが、大人になってからの食の楽しみにつながっていきます。
人が生きていく上で、食事は必要不可欠です。元気に楽しく生きていくためには、食への興味や楽しみが欠かせません。
ぜひこちらの記事を参考に、こどもたちが食べることを楽しいと思えるように、味覚を育むサポートをしてあげてくださいね。