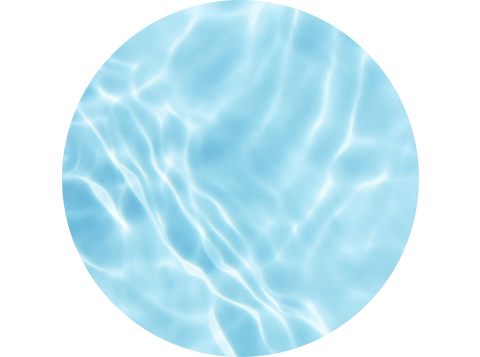水にはミネラル成分が含まれていることは当たり前のように知られています。
しかし、どのようなミネラル成分が含まれていて、どれくらいの量のミネラルが含まれているのかを知らないという方も多いのではないでしょうか。
また、ミネラル成分は健康的な身体を作るうえで重要な役割を果たす一方で、過剰に摂取してしまうと健康に悪影響を及ぼしてしまうため、自分がどれくらいのミネラルを摂取すべきなのかを把握することが大切です。
そこで本記事では、水に含まれるミネラル成分の詳細や水道水に含まれるミネラル成分などについて詳しく解説していきます。
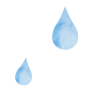
( 1 of 6 )
水にはどんなミネラル成分が含まれているの?
その名のとおりミネラルウォーターにはもちろん、私たちが普段から何気なく使用している水道水にも多くのミネラル成分が含まれているのです。
そもそもミネラルとは、炭水化物・脂質・タンパク質・ビタミンと並んで私たちの身体を作るために欠かせない「5大栄養素」として知られており、100種類以上存在していると言われています。
そんなミネラル成分ですが、水の中には主に下記の4つのミネラル成分が含まれています。
①カルシウム
②マグネシウム
③ナトリウム
④カリウム
それぞれミネラル成分がどのようなはたらきをするのか詳しく解説していきます。
ミネラル成分①:カルシウム
カルシウムは私たちの身体にもっとも多く含まれるミネラル成分で、骨や歯などを形成しています。
カルシウムが不足してしまうと骨の形成に大きな悪影響を与えてしまうため、十分に摂取することが必要です。
ミネラル成分②:マグネシウム
マグネシウムは骨や筋肉、脳、神経などに存在するミネラル成分で、エネルギー生産や栄養素の合成・分解などに大きく関わっています。
300以上の酵素の働きを助ける補酵素としての役割も果たしている大切なミネラル成分です。
ミネラル成分③:ナトリウム
ナトリウムは主に細胞の外の体液に含まれるミネラル成分で、細胞外液の浸透圧を調整する役割を担っています。
主に塩分から接種されるミネラル成分ですので不足することは少ないですが、摂取しすぎると高血圧や胃がん、食道がんなどのリスクが高まると言われています。
ミネラル成分④:カリウム
カリウムは筋肉機能や酵素反応など、カラダのさまざまな調節を担っているミネラル成分です。
また、ナトリウムと作用して細胞の浸透圧を維持する役割も担っています。
( 2 of 6 )
水によってミネラル成分の含有量は異なる?
水によってミネラル成分の含有量は大きく異なります。
水の種類を大きく分けると「軟水」と「硬水」に分けることができますが、実は水の種類を分ける基準になっているのがミネラルの含有量であるため、軟水と硬水によっても大きくミネラル成分の含有量は異なるのです。
「軟水」は硬度0~120mg/Lの水を指し、「硬水」は硬度120mg/L以上の水を指しますが、この数値がミネラル成分の含有量を表している訳ではなく、『(カルシウム量mg/L×2.5)+(マグネシウム量mg/L×4)』という硬度を決める計算式に当てはめられて算出されています。
つまり、硬度をチェックすることで水に含まれているミネラル成分のおおよその量は分かるものの、どのミネラル成分がどれくらい含まれているかを確認することはできないのです。
とはいえ、ミネラルウォーターなどであれば、それぞれのミネラル成分がどれくらい含まれているのか記載されていることも多いため、気になる方はチェックしてみるといいでしょう。
( 3 of 6 )
水道水には
どれくらいのミネラル成分が含まれている?
日本の水道水ではカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分の含有量は300mg/L以下に基準値が定められているため、水道水に関してはこれ以上のミネラル成分が含まれることはありません。
とはいえ、平成30年度に発表された「水道統計 水質分布表(浄水(給水栓水等))平均値」によると、日本の水道水に使用される水源を調査した8,271の計測地点のうち、95%を占める7,917の地点で硬度100mg/L以下となっているため、基本的に日本の水道水では軟水が使用されていると考えておきましょう。
( 4 of 6 )
地域によっても
水道水のミネラル含有量は異なる?
先ほどもお伝えした通り、水の硬度によってミネラル含有量は異なります。
水道水の水源は河川水・ダム湖水・湖沼水・地下水など、いくつかの水源が利用されているため、同じ水道水でも地域によってミネラル含有量は異なります。
例えば、水道水に含まれているミネラル成分の調査結果を公表している岡山県倉敷市の「酒津系浄水場」と「福井系浄水場」のミネラル含有量を比べると下記の表の通りになります。
| 福井系浄水場 | 酒津系浄水場 | |
| カルシウム | 29.7mg/L | 17.0mg/L |
| マグネシウム | 10.2mg/L | 2.4mg/L |
| ナトリウム | 45.7mg/L | 6.7mg/L |
| カリウム | 4.9mg/L | 1.4mg/L |
このように、同じ市内の水道水であっても、水源が異なるだけでミネラル含有量に大きな差があることがわかります。
( 5 of 6 )
水を飲み過ぎると
ミネラルの過剰摂取になる?
結論から申し上げますと、水を飲むだけでミネラルの過剰摂取になる可能性は極めて低いです。
というのも、日本の水道水のほとんどはミネラル成分の含有量が比較的少ない軟水ですし、そもそも水には過剰摂取につながるほどのミネラル成分は含まれていないからです。
ミネラル成分を過剰摂取し続けてしまうと高血圧や動脈硬化、尿管結石などの健康被害のリスクが高まってしまいますが、水を飲むだけで過剰摂取になることは極めて少ないため、日頃の食生活で摂取するミネラル成分を見直すといいでしょう。
( 6 of 6)
1日にどれくらいのミネラル成分を
摂取するべきなの?
1日あたりに必要なミネラル成分の推奨摂取量について、厚生労働省は下記の通り発表しています。
・カルシウム:男性650mg〜800mg・女性650mg〜700mg
・マグネシウム:男性340mg〜370mg・女性270mg〜290mg
・ナトリウム:男性750mg未満・女性650mg未満
・カリウム:男性3,000mg以上・女性2,600mg以上
このように、1日に推奨されている摂取量を水だけで摂取しようとすると10L以上の水を飲まなくてはいけない場合もあるため現実的ではありませんし、同時に少し水を飲みすぎたくらいではミネラルの過剰摂取にならないこともわかります。
ですので、水からのミネラル摂取をメインとしないで、基本的には食事から摂取することが大切です。
(summary)
水を飲んでミネラル成分を補いましょう
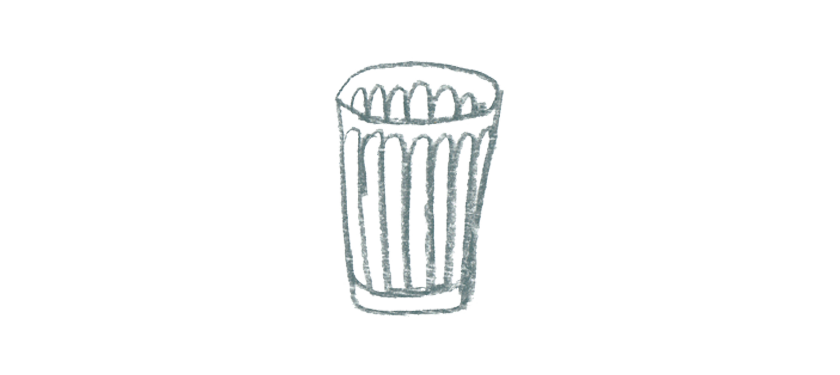
最近、水からミネラル成分を摂取しようと考えている方も多いかもしれません。
しかし、本記事でお伝えしたとおり、水道水にはそれほど多くのミネラル成分は含まれていないため、ミネラルを摂取する目的で飲むことはおすすめではありません。
もし水から効率的にミネラル成分を摂取したいのであれば、ミネラル成分が豊富に含まれているミネラルウォーターや硬水(主に海外の水)を選ぶことがオススメです。
ただし、ミネラル成分が多く含まれている硬水は日本人に馴染みがなく、味が苦手という方や飲むとお腹を下してしまう方もいますので注意しましょう。