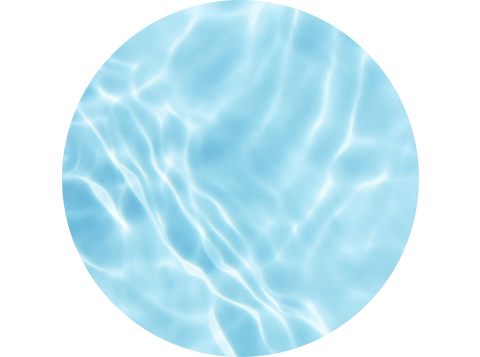もしもに備えよう!
「災害対策として水を備蓄したいけれど、どのような方法ですればいいかな」
「ウォーターサーバーがあれば、もし断水しても安心?」
とお悩みの方はいらっしゃいますか?
地震や台風などで水が出なくなり、飲み水が足りなくなった…というのは、備えておかなければ誰でも経験する可能性のあることです。
そこでこちらの記事では、災害対策のためのウォーターサーバーの上手な選び方や災害対策にウォーターサーバーを活用するメリットなどを紹介します。
災害対策の水の備蓄方法にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

( 1 of 3 )
災害対策のためのウォーターサーバーの選び方
はじめに、災害対策になるウォーターサーバーの選び方を紹介します。
ウォーターサーバーと言っても、さまざまなタイプのものがあります。その中で災害対策をメインに取り入れたい時に、おすすめのタイプをチェックしていきましょう。
期限の長いRO水を選ぶ
ウォーターサーバーの水には、賞味期限の長さ重視のRO水タイプと味や風味の良さ重視のミネラルウォータータイプがあります。
災害対策に最適なのは、より長く水を備蓄できるRO水タイプを選ぶのがおすすめです。
ミネラルウォータータイプの場合、賞味期限が6ヶ月ほどのことが多く、RO水の場合は12ヶ月保存できることが多いです。
災害はいつ起こるかわからないので、少しでも賞味期限が長いRO水の方が安心して備蓄できるでしょう。
停電時でも使えるサーバーを選ぶ
災害時は停電するケースも多いため、電気が通っていなくても使えるサーバーを選ぶのがおすすめです。
具体的には、水を出すところの仕組みがプッシュボタン式のものは、電気を必要とするので使えません。
コック式やレバー式のものを選ぶことで、停電時でも水を出せるのでチェックしておきましょう。
また、下にボトルを設置して使うタイプのサーバーも、水を吸い上げるのに電気が必要なので、上に置くタイプの方が安心です。
少量サイズのサーバーを選ぶ
災害対策のサーバーを選ぶなら、水のボトルが少量なものや、サーバーがコンパクトなものを選ぶのがおすすめです。
ウォーターサーバーは、通常時は電気の力で水を清潔に保っています。そのため、停電してしまうと、水が常温になってしまい開封したボトルは1日程度しか持ちません。
ボトルが大きすぎると1日で飲みきれず、廃棄する必要が出てきてもったいないので、災害対策を重視するなら少量サイズがいいでしょう。
また、コンパクトなサーバーのものなら、避難する際に持っていける便利なメリットもあります。
避難先においしい水を持っていきたいと考えているなら、注目したいポイントです。
( 2 of 3 )
災害対策にウォーターサーバーを活用するメリット
続いて、災害対策にウォーターサーバーを活用することで得られるメリットを紹介します。
災害があった場合、水は生きていくために非常に重要なものとなるので、きちんと備えておいて損はありません。
水の備えにウォーターサーバーを使うことで得られるメリットは、以下の通りです。
ローリングストック方式で常に新鮮な水を備蓄できる
ウォーターサーバーで普段から水を使っていれば、ローリングストック方式で常に新しく新鮮な水を備蓄し続けられるのがメリットです。
ローリングストックとは、常に保存食となるような食材や水分を多めに買い、日々使っては買い足すことで新しいものを備蓄できる方法のことを指します。
ウォーターサーバーを設置して定期的に水を購入し、日々使っては追加することはローリングストック方式での備蓄方法だと言えます。
停電にならなければお湯が出る
ウォーターサーバーがあれば、災害時に電気が通っていれば簡単にお湯が出るのもメリットです。
停電してしまったらお湯は出せませんが、電気が開通すればお湯を使って保存食を食べたり、温かい飲み物を飲んだりできます。
特に寒い時期の災害の場合、少しでも体を温めたいものなので、お湯が出るのは重宝するでしょう。
ボトルの本数と家族の人数で、備蓄するべき水の量がわかりやすい
災害対策をする上での水の量の目安は、1人あたり1日水3リットル、それを3日分備蓄すると安心だと言われています。
4人家族の場合は、1日あたり12リットル、3日分で36リットル必要ということになりますね。
ウォーターサーバーのボトルの分量はサービスによってさまざまですが、1本12リットル前後のものが多いです。
4人家族なら、1本を1日で使い切れるので3本常にある状態をキープできれば、いざという時にも安心ですよね。
反対に家族が少ないなら、少なめのボトルのウォーターサーバーを選ぶと便利に活用できます。
このように、家族の人数と水の備蓄目安量に合わせて、置いておくボトルの量がわかりやすいのが、ウォーターサーバーの災害対策のメリットです。
( 3 of 3 )
災害対策にウォーターサーバーを使う注意点
それでは、災害対策にウォーターサーバーを使う上で、注意しておきたいポイントを解説します。
災害対策にも役立つ便利なウォーターサーバーですが、使用する上で注意したいこともあるので把握しておいてくださいね。
停電したらコンセントを抜く
これはウォーターサーバーだけに限らず、全てのコンセントを使う家電に言えることですが、停電したらまずコンセントを抜くのが大切です。
なぜなら、停電から復旧した際、瞬間的に大量の電流が流れてショートしてしまう危険があるからです。
ウォーターサーバーを災害対策として設置するのなら、実際に災害が起こった時にはまずコンセントを抜くことが重要だということを覚えておきましょう。
停電中は水が清潔に保たれなくなる
ウォーターサーバーの仕組みとして、通電して水を冷やし続けることで、お水の鮮度を保っています。
そのため、停電が長く続いて水が常温状態になると、水が清潔に保たれなくなるので注意が必要です。
もし、停電時に開封済みの水があり、1日で飲みきれない場合は、手洗いや洗顔、トイレ用の水や洗濯など、飲料水以外の使い方で使用しましょう。
災害時には、生活用水も足りなくなる恐れがあるので、ウォーターサーバーの水をうまく活用できるといいですね。
復旧したらしばらく待ってコンセントを挿す
停電が復旧したら、5分ほど電力が安定しているかを確認し、問題がなさそうならコンセントを挿します。
また、もし停電が長く続いたなら、中の水は常温に戻っていて菌が繁殖しやすい状態になっています。
方法はサーバーにより異なりますが、コンセントを挿す前に中の水を抜いてから改めて使いはじめるのがおすすめです。
もし、停電は解消されても断水は続いている、という状態なら、ウォーターサーバーを使って安全な水を確保できるので安心です。
状況に合わせて、うまくウォーターサーバーを活用しましょう。
(summary)
ウォーターサーバーで
もしもの時に備えよう
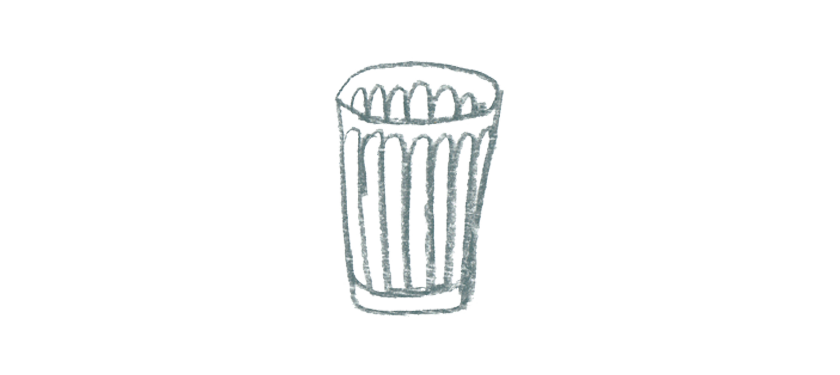
こちらの記事では、ウォーターサーバーを利用した災害対策について、詳しく解説しました。
災害対策に重きを置いてウォーターサーバーを選ぶなら、賞味期限が長いRO水タイプのものにしたり、停電時でも水が出せるタイプにするのがおすすめです。
災害対策にウォーターサーバーを活用するのは、常に新しい水を備蓄したり、家族分の水の目安量がわかりやすかったりとメリットが多いです。
また、実際に災害が起こり断水した時に、飲み水や生活用水に困らず暮らせるのは大きな安心になります。
災害対策の水の備蓄方法に悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。